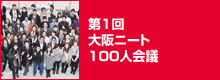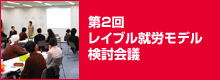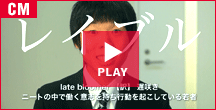![]()
2012年1月26日
第3回 レイブル就労モデル検討会議会議レポート
REPORT 01大阪一丸の想いを伝える

「大阪ニート100人会議」「第2回レイブル就労モデル検討会議」を経て、2012年1月26日、企業による第3回レイブル就労モデル検討会議が終了した。この会議は、レイブルの若者やニート・ひきこもりに関する支援活動を行う支援団体の就労モデルの検討内容を企業に届け、実際の就労に結びつけるためのどのようなクリアすべき課題があるのか、どのような方法や体勢なら就労モデルの実現の可能性があるのかということを探り、実現に向けての打診を行う会議として実施された。
まずは、大阪一丸というプロジェクト自体が生まれた社会的背景や、レイブルの実態、行政や支援団体が取り組むニート・ひきこもり問題に対する様々な施策等を、各関係者からプレゼン形式でお伝えした。そしてその後、学術的な視点から「レイブルの就労モデルの可能性」と題し、法政大学 社会学部准教授の樋口明彦先生より、インターネット中継を通して、就労にまつわる若者と企業のニーズの実態や求められる理想的な就労環境、「大阪ニート100人会議」「第2回レイブル就労モデル検討会議」から生まれた就労モデルについてプレゼンいただいた。

樋口先生からは、様々な統計に基づきながら、「若者を職場で働かせる」というよりは「若者を職場で育てる」という考え方へシフトすることの重要性を発表いただき、支援団体を介してレイブルと企業のニーズを無理のない形でマッチングさせていくこと(それぞれの実情にいかに配慮するか)の例として、第2回レイブル就労モデル検討会議で支援団体の皆様から生まれた就労モデルのご説明をいただいた。
印象的だったお話のひとつに、日本に古くからある「縁故就職」という形が、レイブルの就労支援にも適応できるのではないかという内容があった。信頼できる人からの“お墨付き”の紹介によって、安心感のある人材確保ができるというものだ。支援団体が企業と深い関係性を築き、「この若者だったらきっとあなたの会社に貢献します。」という一種の“レイブルの保証人”となって縁故就職に結びつけるという考え方だ。第2回レイブル就労モデル検討会議の際に挙った「レイブル保証人制度」がまさにそれに当たる。
職場の人間関係や働き方に馴染めなかった経験から就職活動に対して臆病になっていたり、幾度も就職活動にチャレンジしようとするものの履歴書が埋まらず立ち止まってしまうなど、レイブルの実態はその個人によってさまざま。ひとりひとりの実態に寄り添った支援の形が求められている。