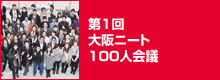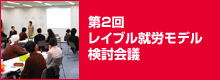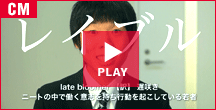![]()
2011年12月15日
第2回 レイブル就労モデル検討会議会議レポート
REPORT 02就労モデル実現への課題

そして、前回の「大阪ニート100人会議」にご参加くださったレイブルの若者の意見と、これまでの支援の中で見えてきた企業のレイブル就労に関する実態を踏まえ、現状の課題も発表していただいた。
■ レイブルの就労にあたっての課題
- ニート支援に関しての法整備が進まない中、公的な事業においては短期間での就労達成が目標とされたり、就職活動を始めても失業者の方との競合があり採用が困難な状況となっている。
- 即戦力が求められ、職務経験のないニートには採用が困難な雇用情勢
- 効率重視の現場においては、作業スピードが求められ、職業経験のない(または浅い)若者にとっての負担感が大きい
- ニートのイメージが極端に悪く、わがままな怠け者と先入観を持つ企業も少なくない。彼らの実態が正しく伝わっていない。支援の必要性を社会に理解してもらうことがまずは必要
- 大企業においてはコア社員の絞り込み、中小企業においては即戦力が求められており、また、自営セクターが減少する中で、企業における人材育成機能が低下している
■ どのような環境がレイブルの就労に必要か
- いきなりフルタイムの正社員はハードルが高い。サポート付きの就労訓練(無償→有償)からアルバイト、正社員というステップが必要と感じる
- 仕事を覚えるまで、「仕事を教え」、「仕事がこなせるまで待つことが可能」な職場環境
- 同じ職場で、職場体験⇒実習(交通費支給)⇒実習(最賃以下の賃金)⇒採用(最賃等適用)など、体験から採用まで一貫した就労支援策
- できるだけ規則正しい時間帯で働ける環境
- 上司の理解のある職場環境(突き放しよりも寄り添い形上司)
- いきなりの長時間労働が難しい場合には、短時間から始め、段階的に時間を延ばしていけるような環境が望ましい(それを受け入れてくれる経営者・管理者等)
- ひとつの企業でアルバイトや在宅から始め、段階的に継続就労につながるような形態
- 倉庫ピッキング、検品、郵便局仕分け、スーパー品出し、データ入力等介護ヘルパー、ポスティングなど、概ね単純作業の方がファーストステップとしては適切だが、業務内容に対する誤解も多く、イメージと現実の統合も相談の中では必要
- 一旦就労の段階に入っても、継続的にメンタル支援を行っていける体制
これまでの支援活動やレイブルの若者の声や実態から見えてくる、理想的な支援の在り方。ゆっくりと時間をかけて人材育成していく職場環境が少なくなってきていたり、コミュニケーション能力の高さを求める企業が多くなってきている中、支援団体の皆様は長年試行錯誤しながら支援活動をおこなってこられた。
レイブルの就労を企業に応援してもらうには「メリットが必要だ」という声があることも事実だ。ニート問題に関する行政の支援は、まだまだその制度上の整備が行き届いておらず、これからの施策が期待されている段階。また社会的にもニート問題は、自己責任論で捉えられる風潮が根強い現実もあるが、若者の適正と人材を求める職場のよりよい出会いが生まれていなかったり、それぞれのニーズにミスマッチが起こっていたり、早期段階からの社会人基礎力養成の必要性があったりなど、社会全体で取り組んでいくべき課題も多くあるのではないだろうか。

会議の中では、これまで企業にかけていただいたあたたかい声として、「若者に仕事上の指導をするのが楽しい」という言葉もあったそうだ。レイブルの就労に関し、大切になってくる要素のひとつとして、企業の理解が挙げられる。受け入れ体制や、場合によっては個別のプログラムを策定する必要性が出ることもある中で、「よし!一緒にがんばろう!」と手をとってくださる企業、新しい環境に慣れるまでの“揺れ”につきあってくれる姿勢をもつ企業の存在はかけがえのないものだ。そのような企業の開拓をすすめていくことも私たちの使命である。
実際に若者の働き手を必要としている職場は多くあり、そのような場所を独自の手法で開拓され、若者の就労につなげている支援団体の方もいらっしゃった。